1. ダイエットにおけるたんぱく質の重要性
2. 1日に必要なたんぱく質の量と計算方法
体重や活動レベルに応じた摂取量の目安
たんぱく質は、体を構成する大切な栄養素。特に、筋肉や内臓、皮膚、ホルモンなどの材料となるため、日々しっかりと摂取したいところです。とはいえ、「自分にはどれくらい必要なんだろう?」と迷う方も多いかもしれません。
実際には、体重や日常の活動量によって必要な量は変わると言われています。
たとえば、あまり運動習慣がない方の場合は、体重×0.95gが一つの目安とされているそうです。つまり、体重60kgの方なら約57gということになります。
一方、週1回以上運動している方や筋トレを取り入れている方では、体重×1.62gという計算が用いられることもあるようです。60kgの人であれば、必要量は約97gになります。
年齢や性別による違い
たんぱく質の必要量は、年齢や性別によっても多少異なるとされています。たとえば、高齢者になると筋肉の合成効率が下がるため、同じ体重でも若い人より多く摂取する必要があるといった話もあります。
また、女性と男性では筋肉量やホルモンの関係で、必要量に差があるとも指摘されています。
森永製菓株式会社の健康情報サイトでは、ライフステージに応じたたんぱく質の摂取が健康維持に役立つと紹介されていました。
さらに、TOPVALUのような食品メーカーも、パッケージで1食あたりのたんぱく質含有量を明示することで、消費者が必要量を意識しやすくなるよう工夫しているそうです。
大切なのは、自分の生活スタイルに合わせて、無理なく、そして偏らない形でたんぱく質を取り入れていくことのようです。
#たんぱく質の計算方法
#運動レベル別たんぱく質
#年齢とたんぱく質摂取
#体重からの必要量目安
#食品表示の活用方法
(引用元:https://www.nipponham.co.jp/tanpaku-mirai/enjoy/02/)
3. 効果的なたんぱく質の摂取タイミング
1日3食で均等に摂取する重要性
たんぱく質は、「たくさん摂ればいい」というものではないようです。実は、1回に吸収できる量には限度があると言われていて、1日の中で分けて摂ることが推奨されているそうです。
とくに日本人の食生活では、夕食にたんぱく質が集中しがちで、朝や昼は不足しているケースが多いようです。
1日3回の食事でたんぱく質をバランスよく摂ることで、筋肉の合成を安定してサポートできる可能性があるともいわれています。
朝食でのたんぱく質摂取の効果
「朝はあまり食欲がなくて…」という声もよく聞きますが、実は朝こそたんぱく質が大事だと考えられています。睡眠中に体はエネルギーを使っているため、朝にたんぱく質を補うことで代謝のスイッチを入れるサポートになると紹介されていました。
たとえば、卵や納豆、ヨーグルト、かまぼこなど、簡単に取り入れられる食品を組み合わせてみると、無理なく摂取できるとされています。
間食や運動後の補給タイミング
たんぱく質は3食だけでなく、間食や運動後にも摂るとよいとされるタイミングがあります。
運動後は筋肉がたんぱく質を必要とする時間帯で、「ゴールデンタイム」とも呼ばれることがあるそうです。このとき、プロテインやゆで卵、魚肉ソーセージなどを取り入れると効率的だと言われています。
また、小腹が空いたときにお菓子を食べる代わりに、低糖質で高たんぱくな食品を選ぶと、無駄なカロリーを抑えつつ栄養補給ができると考えられています。
#たんぱく質の摂取タイミング
#3食均等にたんぱく質
#朝食と代謝の関係
#運動後プロテイン補給
#間食に高たんぱく食品
4. 高たんぱく・低脂質な食材の選び方
おすすめの食材例
ダイエット中にたんぱく質をしっかり摂りたいけれど、脂質はなるべく控えたい。そんなときは「高たんぱく・低脂質」の食材を選ぶのがポイントだと言われています。
たとえば、鶏むね肉は定番のひとつ。皮を外すことで脂質がぐっと減るそうです。白身魚も、脂が少なく消化にもやさしいため、和食にも取り入れやすいとされています。ほかにも、豆腐や納豆といった大豆製品、卵、無糖のヨーグルトなどもたんぱく質源として役立つようです。
鈴廣かまぼこでは、魚由来のたんぱく質を多く含む練り物製品も紹介されており、手軽に取り入れられる選択肢として注目されています。
調理法の工夫
どんなに優秀な食材でも、調理の仕方によって脂質の量が大きく変わることがあるようです。
たとえば、揚げ物にしてしまうと余分な脂が加わるため、ダイエット中は避けた方がよいとも言われています。一方で、「蒸す」「茹でる」「焼く」といった調理法なら、余計な油を使わずに済むため、脂質を抑えた仕上がりになるようです。
味の素株式会社のサイトでも、素材のうま味を引き出しながら、栄養価を保つ調理法が紹介されていました。
植物性と動物性たんぱく質のバランス
動物性たんぱく質は、必須アミノ酸のバランスが整っているという特徴があるとされています。一方、植物性たんぱく質は脂質が少なく、食物繊維なども一緒に摂れるメリットがあるようです。
どちらか一方に偏るより、両方をバランスよく取り入れることが望ましいとも考えられています。
たとえば、朝は豆腐や納豆、昼は鶏むね肉やかまぼこ、夜は魚といった形で、1日の中で組み合わせていくと無理なく実践できると言われています。
#高たんぱく低脂質食材
#ダイエット中の調理法
#鶏むね肉と白身魚
#植物性たんぱく質
#バランスの良い食事選び
(引用元:https://www.kamaboko.com/fishprotein/articles/diet/)
(引用元:https://www.kamaboko.com/fishprotein/articles/muscle/)
5. たんぱく質摂取時の注意点

女性ならではのお悩みの解決のため、これまで学んだ知識と経験から「痛み」「栄養管理」「ダイエット」などを提供しています。
主に鍼灸治療、徒手を用いた姿勢改善、分子栄養学からの健康管理を得意としており、体の内部からのケアも行います。
日本を代表するアスリートの施術経験もあり、治療という視点だけでなく、健康管理にも重点を置いてアプローチしています。
皆様の「未来を創る」ため、健康パートナーとしてお手伝いさせていただいています


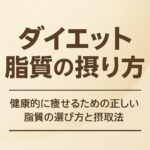



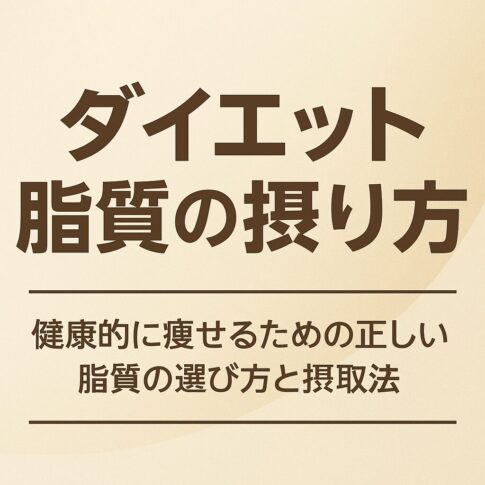







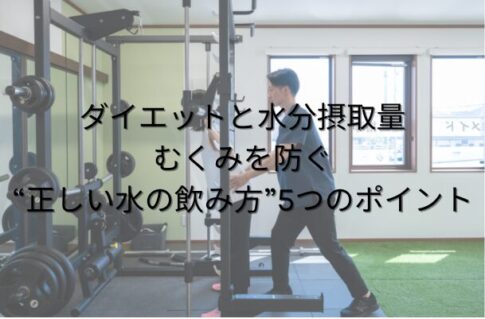



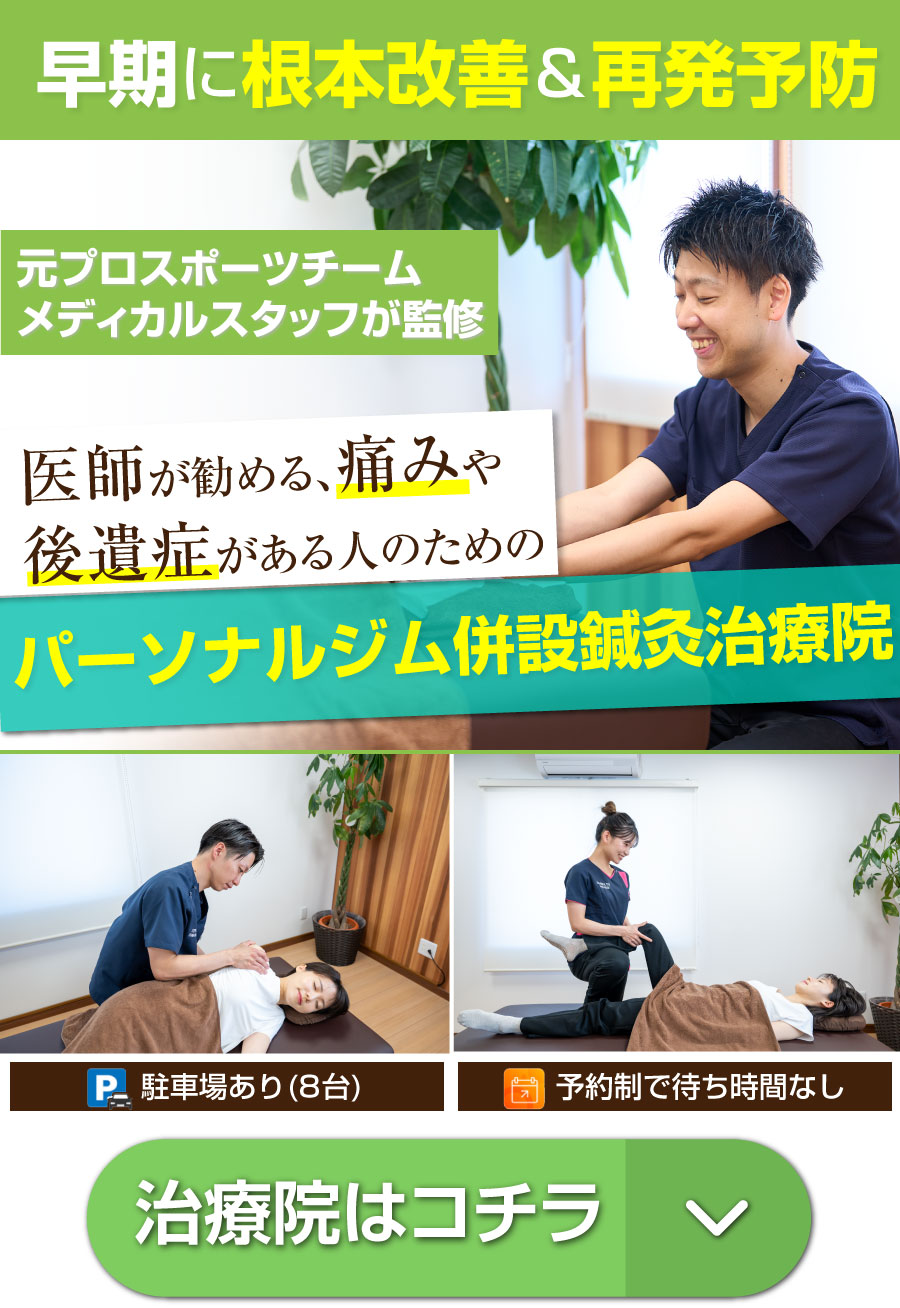

コメントを残す